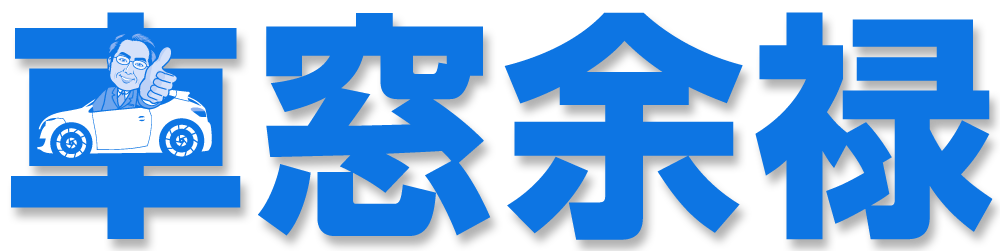
四国の道を車で走ると、沿道を歩む外国人歩き遍路をよく見かける。二人連れが多いが、一人歩きや三人以上も見かける。女性の一人歩きはたまにいるがさすがに少ない。外国人と言っても、このコロナ禍以降は白人の巡礼姿がほとんどである。米国人もたまに出会うが圧倒的に欧州人が多い。車窓から見ると、彼らは長身であり、歩の進め方が彼の地スタイルであるからすぐ分かる。膝を余り折らずに、腰の回転で長い脚を繰り出す歩きである。日本人の歩きとは異なる。
道の駅やコンビニで休息している彼らからよく声がかかる。「英語かまいませんか?」と話しかけてくる。具体的な話であるが、早朝に道の駅日和佐前のファミマでコーヒーを飲んでいると、次々に外国人の遍路がやってくる。ヨーロッパ諸国から、ほぼ全ての国の遍路に出会った。なぜ、そのファミマに多いかと言えば33番札所の薬王寺があり、日和佐の街中に外国人に人気の宿があると聞く。そんな彼らが朝食後にコーヒーを飲みに来る。
さて、彼らは何を求めて八十八ヶ所巡礼の旅をするのか。多くの人にこの問いを投げかけてみた。まず、先祖供養とか家族の健康祈願とか言った日本人伝統の目的はないようである。簡単にいうとやはり「自分探し」であろうか。加えて、「心の重荷降ろし」も比較的よく聞く動機である。異国の物珍しい伝統を単純に歩いて体験してみるという「お気軽遍路」も少ないが存在する。私の経験では、近隣のアジア諸国の巡礼はお気軽タイプが多いような気がするが、文化的に遠い欧米の巡礼にはシリアスな自分探しや重荷降ろし、さらには欧米のキリスト教背景の伝統・文化に限界を感じて別物を求めて遍路巡礼を歩く人が多いように感じる。
ところで、遍路とは「辺鄙な道」という意味だけあって、人気(ひとけ)の多い所は通らないので英語で話せる日本人に遭遇しづらい。それゆえ、彼らの想いや旅の印象を地元の日本人に話したい潜在欲求もある。話が発展して、過去に背負ってしまった人生の重荷について語り始める巡礼もいる。世界中、いずこにも重い人生があると痛感する。
彼らが喜ぶエンタメは「弘法大師にまつわるエピソード」である。ここで、その中でも人気の高いネタを一つ披露したい(笑)。往来に難儀を極めた中国長安の留学から帰った弘法大師は四国の各地に寺を建立して回った。ある町に着くと裕福な家が悲しみに包まれていた。どうしたのかと問うと、家人が大切に育てていた幼子が病気で急死したという。幼子の亡骸が寝ている部屋に案内されると、弘法大師さまは懐から小さな黒石を取り出すと、冷たくなった幼子の手のひらにそっと置き静かにそれを閉じた。そして、手を合わせて祈りをすると「近いうちに良きことがあるでしょう」と述べて去っていった。
やがて、若い母は次の子を懐妊した。そして翌年元気な赤ん坊を生んだ。よく見ると、赤子の片方の手は閉じられていた。産婆がそっと開けると、あの黒石が手のひらに載っているではないか。赤子の母や父を始め家人全員は驚嘆して黒石をしばらく見つめていたが、一斉に歓喜の声を上げてあの幼子の帰還を喜んだ。弘法大師さまがこの子を連れ帰ったのだ。大師様が奇跡を起こしたのだ。
そういえば、中東の地でイエスキリストも多くの奇跡を起こした。歌劇の「ジーサス・クライスト・スーパースター」だ。私たちも負けていない、四国の地には『弘法大師スーパースター』がいる。このタイトルで映画を作りたくなった。 (終)
2024年7月20日 発行

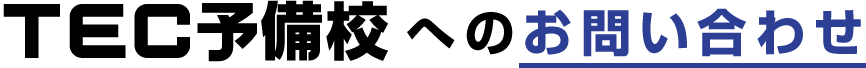
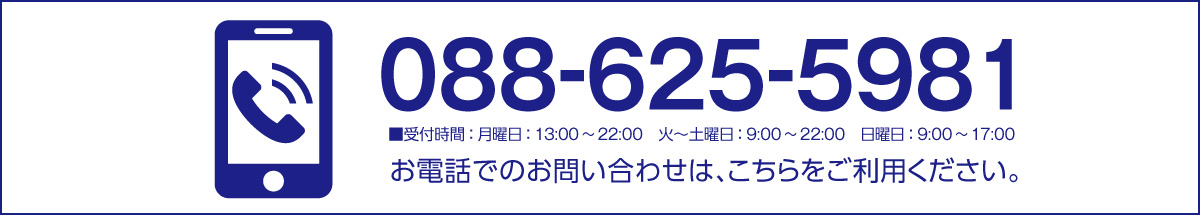

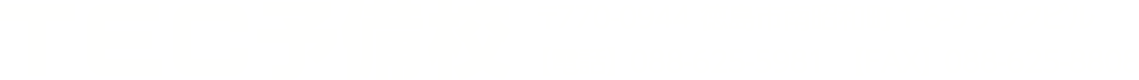 Copyright (C) 2004 - 2025 TEC-Yobiko co.ltd All rights reserved.
Copyright (C) 2004 - 2025 TEC-Yobiko co.ltd All rights reserved.