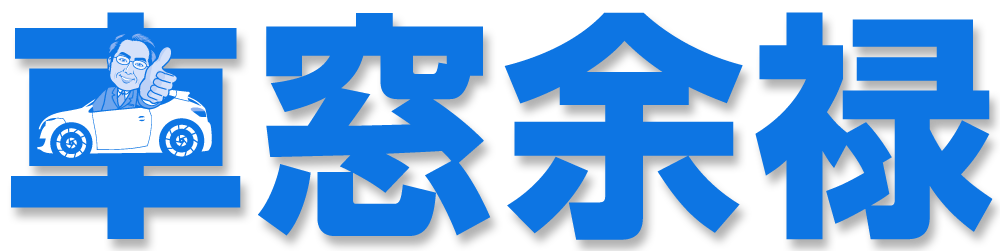
秋の祭りのご馳走に「鯵の姿寿司」が並ぶ。村々では、神社の本殿から聞こえてくる神楽(かぐら)を遠くに聞きながら、各家庭で卓上の大皿に鯵の姿寿司が並ぶのをじっと見つめる子供たちの姿がまさに日本の秋の風物詩である。最近では、鯵の姿寿司はほぼ一年中スーパーの商品棚に並ぶ。便利になったが、風情は失われた。
姿寿司の対局は江戸前寿司である。姿寿司は文字通り、魚の姿全容が現れるので分かりやすいといえば分かりやすい。敏感な子供たちや初来日の外国人を見た目でギョッとさせることもある。反対に、江戸前寿司は職人の巧みな包丁さばきで美しい切り身におろされているので、見た目は完璧である。
姿寿司は、二部構成で作られる。まず、魚の下ごしらえである。背開きにして水酢に漬けておく。その間に、「水、酢、(時に、風味として柚子酢を少々)、塩」を調合して、この中に一定時間魚本体を漬け込む。説明不要と思うが、各調味料の配分や漬け汁の濃度や漬け時間は料理人の判断による。次に、酢飯である。すし飯は一般的に新米より水分の少ない古米が適していると言われる。炊いた米飯を「酢、塩、砂糖、みりん」の調味汁で混ぜ合わせて適度に冷ます。最後に、酢飯を握り、トップに鯵姿を載せる。その上に、甘酢ショウガやすだちの輪切りをのせて完成である。
残念ながら、先の調理法を用いて本来の味の姿寿司を作れる人は、今はとても少ない。スーパーやコンビニに並んでいる鯵の姿寿司は、もはや昭和30年代に家庭で味わったものとは程遠い代物である。何が違うのか。使っている食材に差はない。調味料の「酢、塩、砂糖、みりん、風味のゆず酢」なども基本的には同じであるが、流通品には腐り予防の食品添加物が入っている。製造過程の微妙なすし飯の混ぜ方なども違うように思われる。「家庭料理の母の愛」などに言及し始めると考察は一気に科学的考察外に出てしまう。給食工場で商品としてシステマティックに量、コスト、納期を厳格に守って生まれる食商品は便利な反面どこか物足りない結果になるのかもしれない。作り手の問題を越えた社会問題かもしれない。
私の知人で食に詳しくかつうるさいKさんは自然にも造詣が深く、森林浴を求めよく上勝町へ向かう。彼は、帰りには同町の農産物直売所でもある「一休茶屋」に必ず立ち寄る。お目当ての商品がいくつかあるのだ。その一つが、例の「鯵の姿寿司」である。彼は大好物である。筆者も上勝番茶を買いに出かけたついでに、「上勝鯵の姿寿司」を買い求めた。昼食に店前の展望テーブルに腰かけて食べた。うまい、間違いなくうまい。立派な寿司屋の匠が握ったうまさというより、子供の頃母や近所のおばちゃん達が作ってくれたうまさであった。店長に作者について尋ねると、町内に生まれ育ち嫁いだ高齢の女性だという。「とても美味しかった」と伝えてくださいとお願いすると、はい必ずと笑顔が返ってきた。 (終)
2024年12月5日 発行

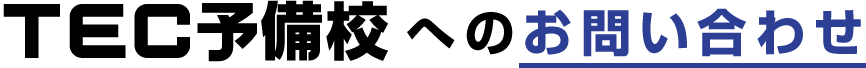
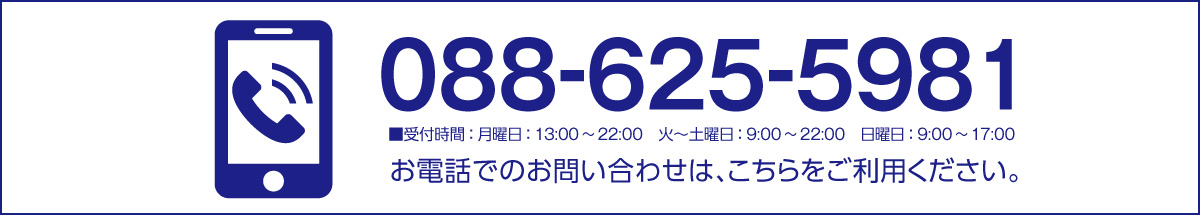

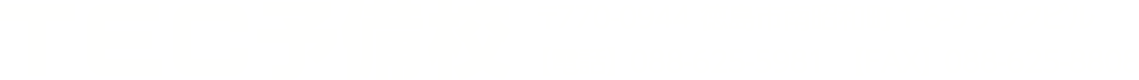 Copyright (C) 2004 - 2025 TEC-Yobiko co.ltd All rights reserved.
Copyright (C) 2004 - 2025 TEC-Yobiko co.ltd All rights reserved.