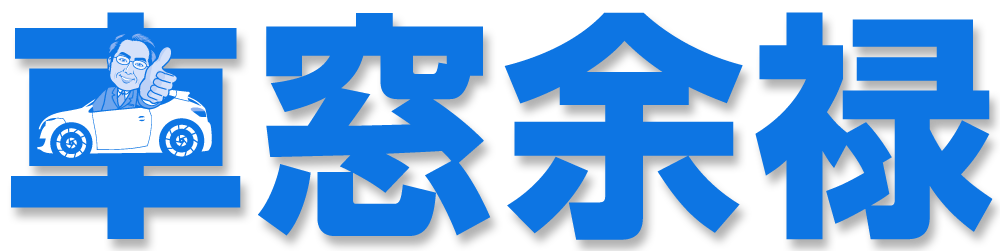
美味しい日本料理は二つの場所から生まれる。一つは由緒ある日本料理店の厨房で働く修行を積んだ和食の匠たちによって生まれる。もう一つは、何代にも亘って母から娘に受け継がれてきた家庭料理である。
日本料理店、つまり料亭の味はプロの味である。閉ざされた厨房の中で育まれた食文化である。食材の吟味から、それら材料の持ち味を生かす下ごしらえから、入念な味、風味、見た目に妥協なき調理工程、そして出来上がった料理の盛り付けから客の元へ運ばれていくまでの温度管理まで抜かりない。匠の研ぎ澄まされた五感とフル回転の頭脳力と気遣いが一品に凝縮されている。筆者は、和食料理人こそ最上位の職業と信じている。
日本の家庭料理は、料亭のそれよりもオープンな環境で育ってきた。家庭の台所で料理は作られるが、祭りや冠婚葬祭の機会では近隣の人々や親戚の者も加わっての共同作業である。各家庭の技術や工夫がここで他人にも伝わっていく。従って、家庭の味であると同時に地域の味となって広がる。あらゆる社会交流がそうであるように、声の大きい者が主導権を握る共同調理の場であるが、控えめだが繊細な美味をもつメンバーの技術も静かに観察され各家庭に持ち帰られる。そして、地域の味は徐々に進化していく。
先日、家内と共に鳴門にある隠れ家的お寿司屋さんに行った。カウンターは3カップル6人であった。昼間の席なので、大トロや生エビ、アワビなどの高級ネタはない。江戸前のネタはブリ、マグロ、タイ、蒸しエビ、サーモン、焼きウナギ、出汁巻き卵などベーシックな物だけであるが、本物の寿司である、旨い。お吸い物も本物である。大将は鳴門出身、大阪で修行して活躍後、生まれ故郷の鳴門でマイペースの寿司屋をやっている。左隣のグーグルを見てやってきた岐阜の若夫婦も大満足で、左端の年配の夫婦は寿司が旨いと酒も弾むと昼から上機嫌であった。
私たち夫婦も大将の寿司に満足した後、寿司業界の今後についての話に進んだ。「寿司屋は資本が小さいから、若い子にいい待遇が出来んのが辛いな」と年配の大将が残念そうに言う。私は、これは一店舗、一業界だけでは解決できない課題ですね、と応えた。続けて、「103万円の壁」以外に政治がやるべきことはありますね、というと他の客も大いに頷いた。大好きな寿司には消えてほしくない。
家庭料理の方も食文化の危機に直面している。母から娘へ(父から息子へでもよい)伝承する日本の家庭料理は共働きの中でどう取り組めばよいだろうか。前号で書いた「上勝町の美味しい鯵の姿寿司」は本質を言うと、本物の鯵の姿寿司はついにそこまで追い詰められたのである。作り手の高齢の女性以外の家庭では、共働きで忙しすぎて、また作る技術がなくて成しえない味なのである。
私たちの大切な食文化は、店でも家庭でも追い詰められている。 (終)
2024年12月19日 発行

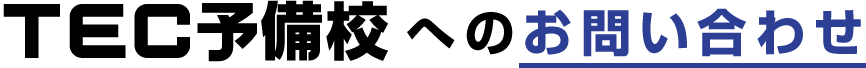
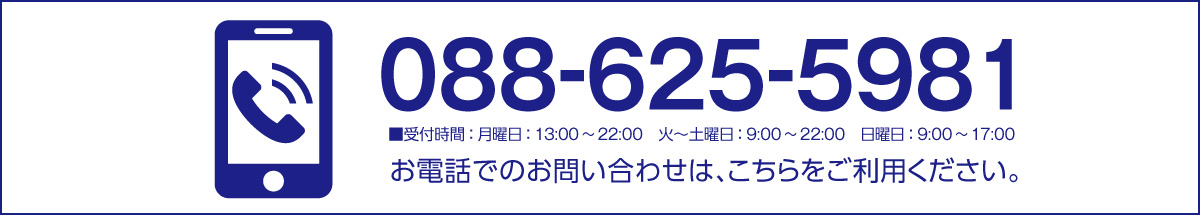

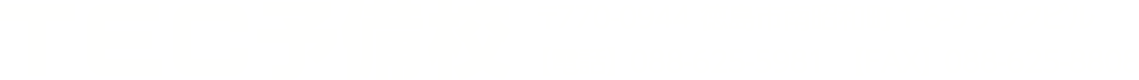 Copyright (C) 2004 - 2025 TEC-Yobiko co.ltd All rights reserved.
Copyright (C) 2004 - 2025 TEC-Yobiko co.ltd All rights reserved.