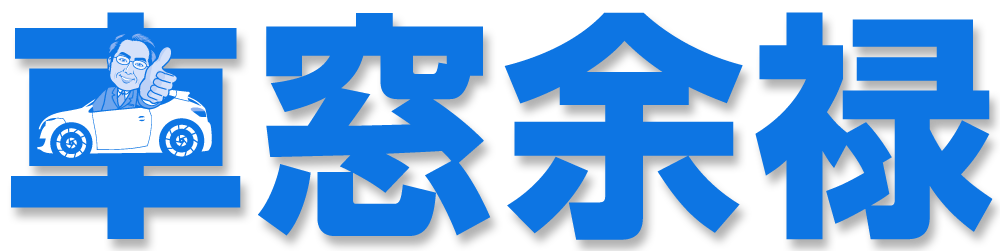
このエッセイがインスタに出るのは令和7年1月2日である。巳年新年の二日目である。まさに正月たけなわである。正月は年の初めで、誠にめでたい時である。言わずもがな、ご馳走のオンパレードの時である。食卓には華やかな料理が並べられ、子供たちがはしゃぎまわる時でもある。
華やかな正月料理は様々あれど、まず雑煮(ぞうに)は欠かせない。雑煮という名の通り、具材は野菜(青菜、人参、里芋)かまぼこなどの練製品の他、魚や肉も使われる。地域や家庭の特色が顕著に表れる料理である。しかし、何といっても、地域や家庭を通して必須の具材は餅である。餅は野菜などとは別鍋で温めた方が完成の見栄えがよくなる。また、網の上で焼いた餅も香ばしさとパリッとした食感で雑煮をさらに引き立ててくれる。
その肝心主役の餅であるが、最近では99%の家庭ではスーパーや和菓子店から買い求めたものを使っている。昭和40年代終わり頃までは、ほぼ農家に限ると思われるが、自前で餅つきをして正月の雑煮料理に備えたものであった。筆者も中学に上がると、父親から餅つきの役目を譲ると言い渡され、重い杵を担いで餅つきに汗を流した記憶がある。「もち米」は普段食事に出る「うるち米」とは同じコメでも種類が異なる。もち米は粘り気が強い成分が多い、または全部である。
食事用のうるち米は水で炊くのであるが、餅の原料となるもち米は水の蒸気で蒸すのである。蒸しあがったもち米はつやつやと色合いもよく熱々でもち米特有のにおいを放っており、餅つき開始の気分が高揚してくる。餅つきをテレビでしか見たことのない人は、蒸し器から石臼に移されたもち米を直ちに「ぺったん、ぺったん」とつくものと勘違いしている節がある。これは違う。餅つきの初工程では杵で蒸しあがったもち米を捏ねて粒をつぶしていく。つぶして粘り気を出していく。これを省いてつき始めると米粒が飛散しまくり、餅つき場は悲惨なことになる。辛抱強く捏ねて粒をつぶして全体がくっつき一塊になったのを見計らって「ぺったん、ぺったん」とつき始めるのだ。工程が進みコメの粘度が上がるとつき音が変わって来る。「ドスン、ドスン」という迫力ある音に変わる。この音を聞くと「そろそろつきあがるな」と嬉しい達成感が湧いてくる。
テレビ等で見た人は気づいていると思うが、餅つきは単独ではできない。満遍なく杵が当たるように塊を回したり、ひっくり返したりする「おで取り」という助手が要る。重い杵を大上段にかぶって思いっきり振り下ろすので、おで取り助手には危険が伴う。なので、ある程度息の合う者同士でなければならない。筆者は母親が助手を担っていた。
傍らには父親が、自分が餅つき役から降りたのと息子の成長を見届けるのと、二重の喜びに浸りながら酒を楽しんでいたのを懐かしく思い出した。
そして、自分がつき上げた餅が雑煮の椀に入っているのをしげしげと見つめたのは感慨深い記憶である。そして、パクっと噛んだ雑煮の餅は大層美味であった。 (終)
2025年1月2日 発行

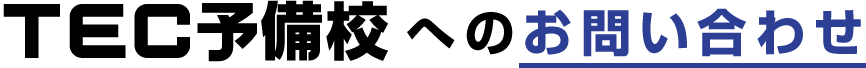
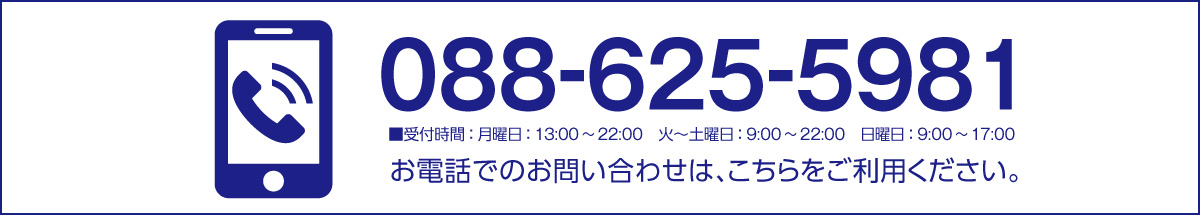

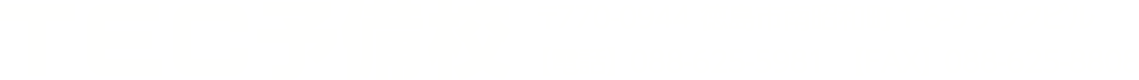 Copyright (C) 2004 - 2025 TEC-Yobiko co.ltd All rights reserved.
Copyright (C) 2004 - 2025 TEC-Yobiko co.ltd All rights reserved.