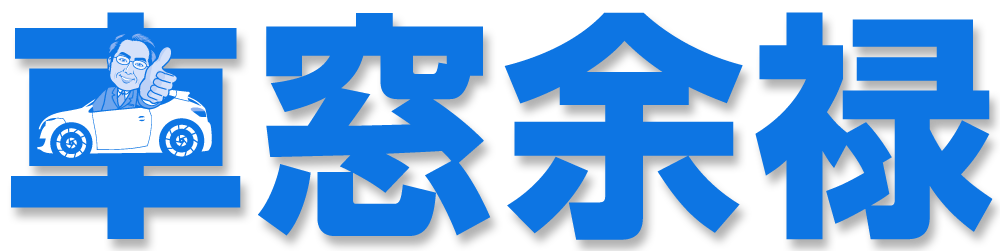
新年正月なので、普段とは違う雑煮を作ることにした。違いは次の二点である。一番目は、普段は味噌汁に少しばかり手を加えて上品な見栄えと味を調えるだけであるが、今回は塩と薄口醤油で味をつけ、透明に近い汁の「お吸い物」に仕上げるのである。二番目は、出汁を煮干しから採るのではなく、昆布と鰹節から採ることである。
実は、ひいきの寿司屋の大将から習った出汁である。そこで出されるお吸い物がシンプルながらとても美味しい。彼に、「家でも作ってみたいなぁ…」と言うと、出汁は煮干しではあかんよと教えられた。昆布でじっくり旨味を出して、後で多い目の鰹節を贅沢に入れて強火で短時間で仕上げるのよ、と教えられた。敢えて聞かなかったが、煮干し出汁では多分個性が強すぎて、繊細な見た目と味わいを特徴とするお吸い物には合わないのだろうと想像した。やはり、適材適所である。
出汁は寿司屋の大将の教えに忠実に丁寧に作った。紙フィルターで出汁を濾して雑味を除き汁の透明感を確保した。最後に、慎重かつ大胆に塩少々と薄口醤油で味付けをした。ここは足し算引き算ではなく一発で決めたかった。料理人の意地である。小皿にとって、味見をしてみた。我ながら、完璧であった。補足しておくが、昆布も鰹節も普通にスーパーで売っているものである。
次に具材であるが、一般的なものを用意した。シャキッとした歯ごたえの青梗菜、赤身の強い金時人参、里芋(これは事情で調理済のを買った)、そして蒲鉾(断面に絵が出るのにしたかったが高額なので、表面が赤と緑の物で我慢した)、そして、そして無くても足りるが黄ユズの皮に拘った。黄ユズは年末で市場が閉まった後で買いに行ったため、どのスーパーも品切れで、四軒目でやっと二個手に入れた。
客人に出すときは緊張する。汁の透明感と具材の姿形が勝負なので、盛り付けと汁の注ぎ込みに注意が要る。点検して問題なしと自己判定出来たら、細長くカットした黄ユズの表皮を一、二枚ここぞと思う地点に浮かべる。「フィニッシュ」と小声で囁く。
客人の反応、感想は気になるが、私は敢えて聞かない。料理人の腕や努力と食する人の評価は無関係なことである。人それぞれでよい。
その翌日昼前ことである。車の新年ツーリングに出かける準備をしていた。腹ごしらえをしなくてはと、冷蔵庫を開けた。前日のお雑煮の具材が残っている。ラッキーなことに出汁も適量ある。餅はたくさんある。出汁を温めながら、多い目の具材を順番に切って、煮時間順に具材を放り込んでいった。一椀で一食だ。
ここで、ふと、うどん県香川の「しっぽくうどん」を思い出した。通常少量のうどん具材ルールを破ってどっさり具材を入れた型破りうどんである。出かけ間際アタフタしているときに生まれたのだな、と閃いた。その瞬間、自分の目の前にある雑煮を「しっぽく雑煮」と命名した。 (終)
2025年1月16日 発行

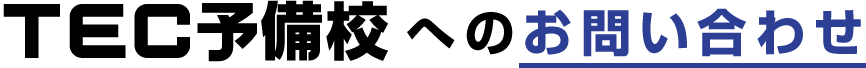
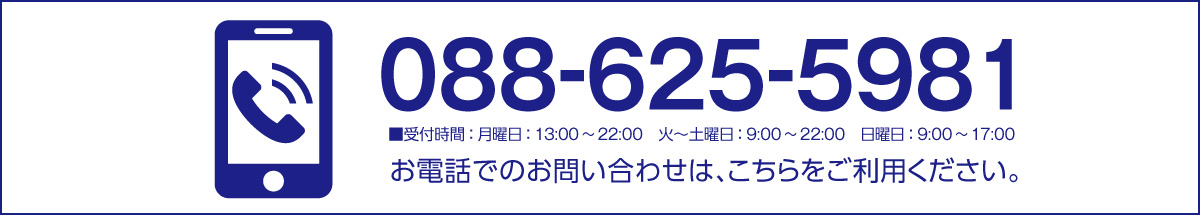

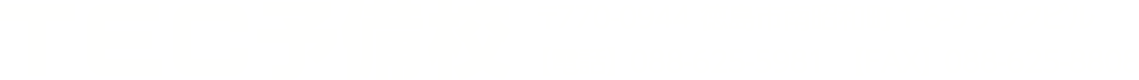 Copyright (C) 2004 - 2025 TEC-Yobiko co.ltd All rights reserved.
Copyright (C) 2004 - 2025 TEC-Yobiko co.ltd All rights reserved.