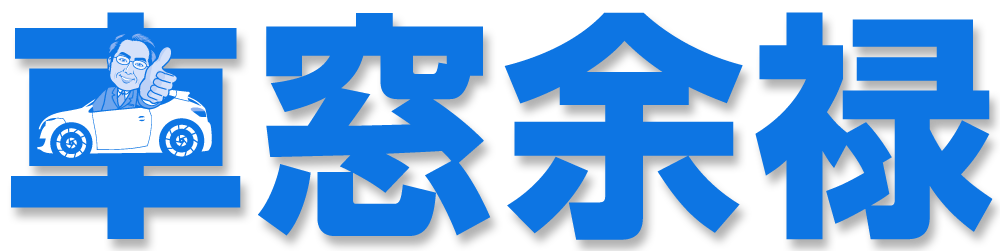
今年も桜の季節がやって来た。淡い桃色の花弁の桜は日本列島に春が到来したことを実感させる象徴と言える。見渡せば、野山に、道沿いに、民家の庭に桜の開花が見えると何かじんわりと嬉しくなる。日本人であること、日本に生まれたことを実感する。
法で定められた国花はないが、サクラ(桜)は日本を代表する花であることは間違いない。菊も国を象徴する花ではあるが、こちらは国家や皇室を連想させる。私たち一般国民が親しみを込めて愛する花はサクラである。植物分類上は、バラ科のサクラ属である。日本に自生する自生種は10乃至11種ある。元来、サクラは突然変異を起こしやすい品種である。なので、野生のサクラも亜種が少なくない。また、観賞用に野生種の中から選抜して開発してきた栽培品種は200種類以上存在する。野山を見ても街中の庭園を見ても、色合いも白から淡紅色や濃紅色まで多岐に楽しめる。
話をサクラの開花に転じたい。徳島の地でも、開花時期が「ばらけてきた」と感じる人が多い。同じソメイヨシノでも地域により開花の時期が違ったり、近くにある木でも時期が大きく異なる場合がある。一本はまだ蕾なのに、別の木は七分咲きになっていたりする。いわゆる「狂い咲き」と言われるが、まだ寒い冬に満開になったりすることがある。寒中なのに早々とサクラが観賞出来て嬉しいと思う人もいるが、少々首を傾げて天候異変のせいではと心配になる人もいる。
筆者が近年「サクラ開花ミステリー」として気になっていたのは二点ある。一つ目は、日和佐と牟岐をつなぐ海沿いルートである南阿波サンラインのサクラ開花時期である。車仲間とツーリングに行っても、徳島市よりも、阿南市よりも、その海沿いルートのサクラ開花が遅いのである。海沿いなので日はよく当たるし、海は大きな熱を蓄えているので常に北の地域よりも気温は高いのに…。車の車外気温の表示をみても、降りて体感しても間違いなく暖かいのである。徳島市の隣人も「徳島のサクラが五分咲きだから、南に行ったらさぞかし見事な満開でしょう」と当然のように話すが、実態は逆なのである。う~ん、不思議だ。なぜだろう??
二つ目のミステリーも同じく南の地にある。日あたりの良い南面のサクラがまだ蕾なのに、比較的近隣地区にある北面でおまけに谷間のサクラが満開になっている。う~ん、同じソメイヨシノなのに…??単なる木の個体差で片づけてよいものだろうか。でも一本や二本の問題ではない。
大分調べた。ネット検索だけでなく、現地へ足を運び、証拠写真も撮った。ようやく分かった。サクラの花芽は冬眠するのである。それは葉から送られる冬眠ホルモンの作用である。そして、翌年春の開花には二つの条件が要る。一つは一定期間の低温の蓄積である。もう一つは、低温蓄積が出来たタイミングでやって来る春の高温である。従って、日のよく当たる場所では低温蓄積が進まないのである。特に、近年の温暖化気候の下では。
同様の現象は九州でも起きている。以前は、サクラ開花前線は南の鹿児島から北上していた。ところが、近年は北から順に南下するようになった。暖かい鹿児島のサクラの花芽は低温蓄積が足りないのである。 (終)
2025年4月10日 発行

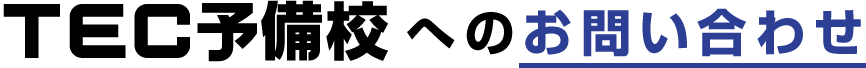
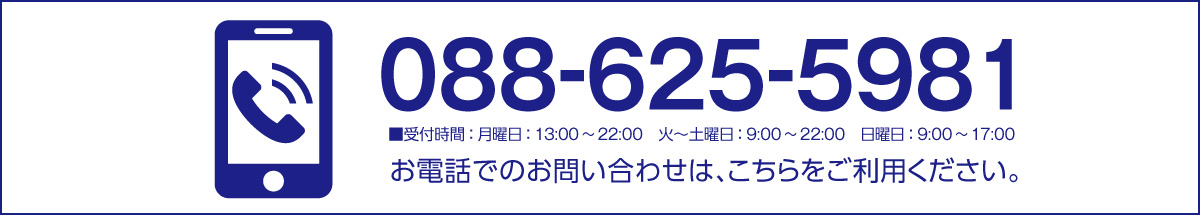

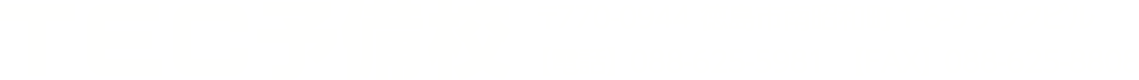 Copyright (C) 2004 - 2025 TEC-Yobiko co.ltd All rights reserved.
Copyright (C) 2004 - 2025 TEC-Yobiko co.ltd All rights reserved.